

| ① 第13回非同盟諸国 首脳会議の 眼目は何か(上) |
② 第13回非同盟諸国 首脳会議の 眼目は何か(下) |
③ イラクに対する 武力行使に 反対する決議 |
④ クアラルンプール 宣言 |
⑤ 「クアラルンプール 宣言」で決定した 実行項目 |
第13回非同盟諸国首脳会議 ④ 2003年2月20~25日 クアラルンプール:マレーシア 非同盟運動のひきつづく再活性化に関する 「クアラルンプール宣言」 |
||||
非同盟諸国首脳会議 【翻訳資料】 (2003年2月25日、日本AALA作成) |
||||
クアラルンプールで開催された第13回非同盟運動諸国首脳会議は、最終日の2月25日、非同盟運動の役割を高めるため、結束と活動の強化をうたった「非同盟運動のひきつづく再活性化に関するクアラルンプール宣言」を採択しました。 以下は、マレーシア国営ベルナマ通信が伝えた宣言の全文の翻訳です(テキストはベルナマ通信のサイトより)。 |
||||
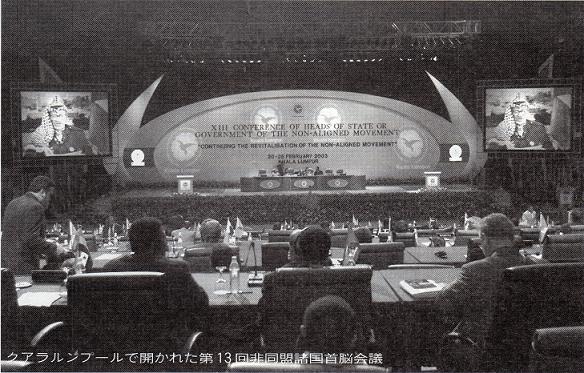 クアラルンプールで開かれた第13回非同盟諸国首脳会議 |
||||
「非同盟運動のひきつづく再活性化に関する クアラルンプール宣言」 |
||||
われわれ非同盟運動の国家・政府首脳は、第13回首脳会議のために2003年2月24・25日にマレーシアのクアラルンプールに集まり、平和で、繁栄し、より公正で平等な世界秩序の確立のために共同の努力を続けるうえで、1995年のバンドン会議でのべられた非同盟運動の理念、原則、目的、ならびに国連憲章にたいするわれわれの永続的な信念と強固な誓約を再確認した。 |
||||
非同盟運動は、とりわけ脱植民地化、アパルトヘイト、パレスチナ・中東情勢、軍縮、貪困撲滅と社会・経済的発展など、加盟国が関心をもつ重要な問題において積極的な、さらには中心的な役割を多年にわたって果たしてきた。 創立から40年以上がたち、多くの難題や変遷を経験してきた今、非同盟運動のいっそうの強化を目的に、時代と新しい現実に沿って非同盟運動の役割、組織、活動方法を包括的に見直すことは時宜にかなっており、適切である。 冷戦の終結、一極性の登場、単独行動主義への傾向、およぴ、国際テロリズムのような新たな難題と脅威という点で、運動にとって、多国間主義を促進し、発展途上国の利益をよりよく擁護し、われわれが置き去りにされないようにすることきわめて重要である。 |
||||
グローバル化の進展および科学技術の急速な進歩によって世界は劇的に変化した。 豊かで強大な諸国が、経済・貿易関係を含む国際関係の性格や方向、ならびに、これらの関係を統べるルールを決める上で過度の影響力を行使しており、その多くは発展途上国を犠牲にしている。したがって、非同盟運動が、運動の今日性と加盟諸国にとっての有用性をひきつづき維持するようなやり方で対応することが不可欠である。 グローパル化は、すべての国の将来と存続にたいし多くの課題と機会をもたらしている。 グローバル化は、現在の形では、発展途上国を置き去りにし、それを増進すらする。われわれは、グローバル化がすべての人々にとって変化のための積極的なカとなり、少数の国ではなく、最大多数の国々の利益となるようにしなければならない。グローバル化は発展途上国の繁栄や権限強化につながるぺきであり、貧困化の継続や、富裕な先進世界への従属につながってはならない。 |
||||
情報通信技術における革命は、世界を急速にかつ根本的に変えつつあり、発達した諸国と発展途上国との間に広大なデジタル上の分断をもたらして、それを広げている。 発展途上国がグローバル化の過程から利益を受けることができるように、分断に橋がかけられなければならない。 発展途上国が、その開発目標を追求して経済を現代化し再活性化するうえで、この新しい技術革新をもっと容易に利用できるようにすべきである。 これらの開発目標を達成するには、それを可能にする国際環境や、先進世界におけるわれわれのパートナーを含め諸国による誓約や公約の順守が求められる。 未来は、過去と同様に多くの課題や機会をもたらす。非同盟運動はひきつづき、強固さと凝集力と弾力性を保たなければならない。 非同盟運動の今日性の維持は、加盟国の結束と連帯、ならびに課題に適合していくその能力に大部分がかかっている。この点で、前回の首脳会議で開始された非同盟運動の再活性化のプロセスにさらに弾みをつける必要がある。 |
||||
言葉を行動に移そうとするわれわれの願いにそい、非同盟諸国運動の基本原則、目的、目標に献身しながら、われわれは、以下のためにあらゆる努力をおこなうことを決意する。 *以下は、次ページ「クアラルンプール宣言で決定した実行項目」に再掲しています。文章の相違は翻訳の相違で他意はありません。 |
||||
・共通の利益および共同のたたかいの歴史にたって結束を強めるとともに、これらの利益を一貫して促進しわれわれの懸案事項に全面的に対処するために、たゆまず努力する。 ・非同盟運動および国連憲章の基本原則を堅持して、国家間の対話と外交を通じて世界平和を維持・促進し、紛争解決のための武力行使を回避する。 ・非同盟運動加盟国ならびに国連加盟国の利益を守る不可欠の手段として多国間プロセスを促進・強化する. ・国際的な意思決定への発展途上国の参加を強化するため、国際的な統治システムの民主化を促進する。 ・非同盟運動加盟国に影響を及ぼすものをはじめ国際情勢にたいして受身ではなく能動的になり、非同盟運動が傍観者ではなくて国際的な意思決定過程の最前線に立つようにする。 ・各国別および集団的な強靭性を高めるため、各国の能力を強化する。 ・政治、社会、文化、経済、科学分野をはじめあらゆる分野で「南南協力」を強化する。 ・建設的関与、幅広い協力、互恵を基礎に、先進国およぴ工業国とのより活力のある協力関係を促進する。 ・市民社会の諸組織、民間セクター、議員が共通目標の達成に向けて建設的役割を果たすことができるとの認識にたって、それらとのより緊密な交流と協力を促進する。 |
||||
| これらの目標を追求しながら非同盟運動の加盟国は、以下の具体的措置の実行に努める。 |
||||
・われわれを分裂させる問題ではなく結末させる問題に焦点をあて、それによって非同盟運動の結末と凝集力を強化することで、加盟国間の共通見解を強めることをめざし、国際問題にたいする非同盟運動の立場についてしっかりした評価と分析をおこなう。 ・非同盟運動の役割を見直して再定義し、焦点を絞った簡潔な文書化の必要性を含め、より効果的で効率的なものにするために、運動の機構と方法を改善する。 ・非同盟運動や加盟国に影響する国際情勢にタイムリーに対処できるように、ニューヨークならびに、必要ならジュネープ、ウィーン、ナイロビその他の中心地における調整ビューロー定期会議を通じて、協調と協力を強化する。 ・トロイカ体制〔前・現・次期議長国〕、調整ビューロー、既存のすべての作業部会や委員会、安保理における非同盟部会など、既存のメカニズムおよび機構すべてを全面的かつ効果的に活用し、適切な新しい機構を創設する。 ・より双方向の会議を通じて非同盟運動定期外相会議をいっそう効果的に活用し、非同盟運動の有効性を増し注目を高めるために他の関連大臣の交流と関与を奨励する。 ・非同盟運動のスポークスマンとして議長国の役割を強化し、必要な支援体制の一環として適切なメカニズムを創設する。 ・グループ77との間で、共同調整委員会(JCC)会議の定期的でより頻繁な開催を通じて、協調と協力を強化し、社会経済問題や開発関連問題で共通戦略を策定する。 ・貧困撲滅、債務軽減、能力強化、エイズなど発展途上国の緊急問題に対処するうえで必須のものとして、国連ミレニアム総会、ならびに、国際貿易に関するドーハ会議、開発資金に関するモンテレー会議、持続可能な開発に関するヨハネスプルク世界サミットなど他の国際会議の諸決定をフォローアップする。 ・地域および地域間の強化された協力、具体的な事業や計画への着手、資源の共有化、「南」の著名人や諸機関の寄与の活用を通じて、「南南協力」を拡大し、深め、充実させる。 ・国や市民社会や民間セクターの加わる協力関係を基礎に、デジタル上の分断に橋渡しをする取り組みにおいて、関連の諸会議を含め、国際協力と連帯のためのメカニズムを促進し発展させる。 ・とくにNEPAD(アフリカ開発のための新パートナーシップ)を通じてアフリカのための、ならびに、後発発展途上国、内陸発展途上国、小島嶼発展途上国のための国際プログラムをひきつづき強く支持する。 ・南北間の理解を広げ、発展途上国に影響する重要な決定がおこなわれる前に非同盟運動の見解が考慮されるようにするために、制度化された接触を含め、既存のおよび適切な新たなメカニズムを通じて、G8をはじめわれわれの開発パートナーとの建設的な対話と交流を促進する。 |
||||
非同盟運動の再活性化というわれわれの目標を達成するなかで、われわれは、国際の平和と安全の維持にとって不可欠の国際組織である国連の強化による多極世界の促進、ならびに、国連憲章に明記されている人権、社会・経済発展、国際法の尊重の促進に向けて、あらゆる努力を尽くさなければならない。 |
||||
| |
||||
| |
||||