

| ① 13回非同盟諸国 首脳会議の 眼目は何か(上) |
② 第13回非同盟諸国 首脳会議の 眼目は何か(下) |
③ イラクに対する 武力行使に 反対する決議 |
④ クアラルンプール 宣言 |
⑤ 「クアラルンプール 宣言」で 決定した実行項目 |
| 第13回非同盟諸国首脳会議 ② 2003年2月20~25日 クアラルンプール:マレーシア |
||||
| 「クアラルンプール 宣言」は 経済の問題も 述べている |
マハティールは 戦争を放棄した 日本国憲法を 最もよく守っている |
非同盟諸国首脳会議に 日本の労働組合、 農民組合、 共産党、原水協の代表が 参加したことの意味は 大変重要 |
||
| 軍事基地撤去、 軍事同盟反対 というスローガン |
首脳会議が 開かれている マレーシアで 「NGO会議」を 開いたことに感動 |
次回の第14回非同盟 首脳会議には、 発言できる資格= オブザーバーとして 参加する |
||
| 秋庭日本AALA理事長に聞く (下) |
||||
第13回非同盟諸国首脳会議の 眼目は何か(下) 重要な日本からの参加と貢献 |
||||
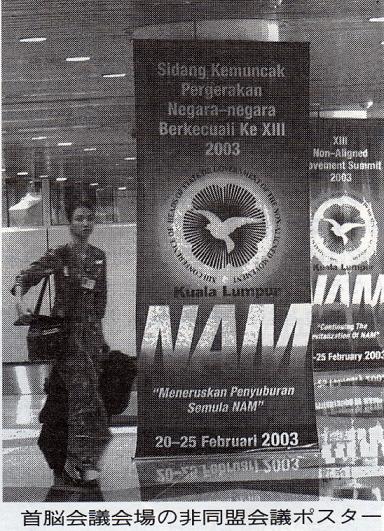 首脳会議会場の非同盟会議のポスター |
||||
「クアラルンプール宣言」は 経済の問題も述べている |
||||
■堀中 アセアンの歴史をみると、70年代に南南協力のひとつの典型じやないかと言われる時期がありました。非同盟運動のなかで南南協力が非常に強調された時期です。 80年代になると、アセアンは外資導入を非常に必死になってやる。多国籍企業を入れて、経済開発をしていこうとし、日本でもその時期から、アセアンは南南協力から多国籍重視に変わってきたんじゃないかという議論があり、ひとつの論点になっています。 しかし私の考えでは、マハティールは、多国籍企業を利用するけれども、それをしっかりコントロールするんだという意識があるんじやないかという気がします。多国籍企業を活用するということと、多国籍企業に屈服することは違うんだということを、これからのアセアンが示していくというふうになってくるでしょう。 これはたいへん重要な、進む道を示すことになると思うんですが。 |
||||
■秋庭 マレーシアで出された「クアラルンプール宣言」は経済の問題も述べているんです。 「具体的なプロジェクトと計画を実行に移し、資源をプールし、著名人や諸機関からの資金を導入し、地域的かつ地域間の協力を強めることによって南南協力を強化する。南北間のより広い理解をもたらし、重要な決定が下される前に運動の諸見解が完全に考慮されることを保障するため、制度化された接触を含め、現存する機構と新たな適切な機構を通じて、先進諸国におけるわれわれのパートナー、とりわけG8諸国と建設的な対話と相互活動を進めること」ーこういうことをうたっているんです。 |
||||
マハティールは 戦争を放棄した日本国憲法を 最もよく守っている |
||||
■堀中 70年代に、国連の総会でNIEO(「新国際経済秩序」)宣言をするわけですけれども、これがアメリカの逆流によってつぶされてしまう。 そのなかで、アセアンの実績をふまえて、マハティールがここで再活性化を宣言していくのは、歴史的に非常に重要な意味をもっているという気がします。 さてそこで、日本の立場とか日本AALAの貢献について、どう思われますか。 |
||||
■秋庭 日本の問題ですね。マハティールですけれども、マハティールは戦争を放棄した日本国憲法を最もよく守っています。その点で、まったく日本の首相とは天地の差。 |
||||
■堀中 日本の首相にしたいですね(笑い) |
||||
非同盟首脳会議に 日本の労働組合、農民組合、 共産党、原水協の代表が 参加したことのもつ意味は大変重要 |
||||
 日本とAAPSOの代表 |
||||
■秋庭 日本政府の対米追随ぶりが、もう痛く感じさせられる毎日毎日だったんです。 AAPSOが提唱、非同盟国際研究所(インド)が主催してやった(2月)23日の「NGO会議」の夕食の時に、パウエル米国務長官が日本を訪問したことが話題となり、参加者から「日本はパウエルに対してどう対応するのですか」と聞かれたんです。 私は外国で日本政府このそういう対応を聞かれたことはあまりないんです。 ところが今回は、どうせ賛成するんでしょっていう、そういう気持ちがありありと見える質問でした。日本政府が(イラク戦争に)賛成しなければ変わるんだがという話になるわけ。 このことと関連して今度の非同盟首脳会議に日本の労働組合、農民組合、共産党、原水協の代表が参加したことのもつ意味は、大変重要なことだったと思います。 ゲスト参加した人たちは、こういう役割をはたしたことについて、日本AALAが営々として活動してきたことによってこういうことがきりひらかれた、これは歴史的なことだという話になりました。連帯委員会はそういう役割を果たすことができて、大変光栄だなと。 ところで、この光栄を誰がつくりあげたかというと、やはり、日本の連帯委員会の長い歴史のなかで、全国に組織をつくって、いろんな活動をして、ここまで連帯委員会の活動を押し上げてきた、全国の組織と多くの会員のおかげで、この歴史的なことを成し遂げることができたのです。 私は、全国の組織と多くの会員に対して、本当に心からの敬意を表したいと思います。 だからこそ、ますます組織建設、財政建設が大切だということと、これからの課題ですけれども、非同盟運動の再活性化に連帯委員会が日本の民主勢力とともに、どう貢献できるか、このことを探求していく必要があるんじやないかなと思っているのです。 |
||||
軍事基地撤去、軍事同盟反対 というスローガン |
||||
■堀中 軍事基地反対、軍事同盟反対で、日本AALAとして、ダーバンでそういうことを宣言のなかにはっきりと明記した。明記するということは、首脳会議に出席している国ぐにがそれを真剣に考えることです。 そういう問題提起をしてきたことは非常に重要だと思うのです。今度のイラク問題でも、アメリカが戦争する、侵略するということは、そのイラクの周辺の国ぐにがやはり軍事基地を提供し、軍事同盟を結ぶ、それがなければ不可能だったわけです。 そういう意味で、今までの非同盟運動なり、アラプ中の資源ナショナリズムの弱点がアメリカによって衝かれた、それが利用された、そして彼らに侵略を許してしまった。 そういうことがあるので、この軍事基地撤去、軍事同盟反対というスローガンはたいへん重要です。それは、日本AALAがずっと非同盟運動に提起してきた課題で、その点については日本AALAの貢献ということですね。 |
||||
■秋庭 今度の「NGO会議」では、そういうことを非同盟運動に提起するということになり、その文書を非同盟首脳会議の書記局のほうに提起することを決めたんです。 |
||||
■堀中 そうですね。「NGO会議」も今度の首脳会議で大変意味があったと思います。インドでもやったし、クアラルンプ-ルでもやったのですから。 |
||||
首脳会議が開かれているマレーシアで 「NGO会議」を開いたことに感動 |
||||
■秋庭 私、非常に感動をおぼえたんですけれども、首脳会議が開かれているマレーシアで「NGO会議」を開いたことに。 そこには、日本、インド、エジプト、スリランカ、マレーシア、世評、世界労連などから40名近くが参加したんです。 軍事基地撤去を含めた決議をして、それを首脳会議に反映させるということになったんです。 こういう会合は、98年のダーバンの首脳会議のときに想像すらできませんでした。 これは連帯委員会がNGOと非同盟運動との結びつきを改めて重視して、「非同盟国際シンポジウム」をみんなで成功させ、そして、アンマンの首脳会議の前に「NGO会議」を開こうと、エジプトとヨルダンを訪問、アンマンで「NGO会議」開催を決める。 それができなくなった、ではどうするかということで、去年の8月から9月にかけてコロンボで開かれたAAPSO提唱のフォーラムに参加し、どうするかを相談して、もしできればクアラルンプールでやろうとなった。ところがクアラルンプールは首脳会議の準備でできない。 それではどこでという相談で、ハイデラバードの「アジア社会フォーラム」の分科会として開かれたNGO国際会議準備の会合に参加することになったわけです。 AAPSO、スリランカ、インドの著名な人たちも参加。そこで、どうしてもNGO国際会議をひらこうということで、今回、とりわけインドの「非同盟国際研究所」の大きな力があって、マレーシアで開くことができました。 3年後の第14回首脳会議の際にNGO国際会議の開催をめざすいうことでは、たいへん貴重な経験をして良かったと思うんです。 |
||||
次回・第14回非同盟脳会議には、 発言できる資格 =オブザーバーとして参加する |
||||
■堀中 そうですね。そういう意味では、これで終わったのではなくて、もう、次はキューバですから、キューバに向けて活動が始まっているんだと、こういうふうに考えないといけないわけです。 |
||||
■秋庭 そうです。もう活動が始まっているということです。 連帯委員会がオブザーバー資格を申請するということについて、実は南アフリカの外務次官と話をしたときに、彼は「それは申請しないとだめだ」と。「申請書を出さなければ検討できない。そうすべきだ」といっていました。 ハバナでの(次回・第14回非同盟諸国)首脳会議の時には、発言できる資格、オブザーバーとして参加する。こうして、日本国民と非同盟運動との結びつきをはかっていくことをめざして活動しなければならないなと強く思わさせられているわけです。 |
||||
■堀中 どうも、帰ってきてすぐ。お疲れのところ、ありがとうございました。 (収録は2003年3月12日) |
||||
*このページは「日本アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会機関誌」2003.5.1No.516から転載(一部簡略化)して作成しています。 |
||||
| |
||||